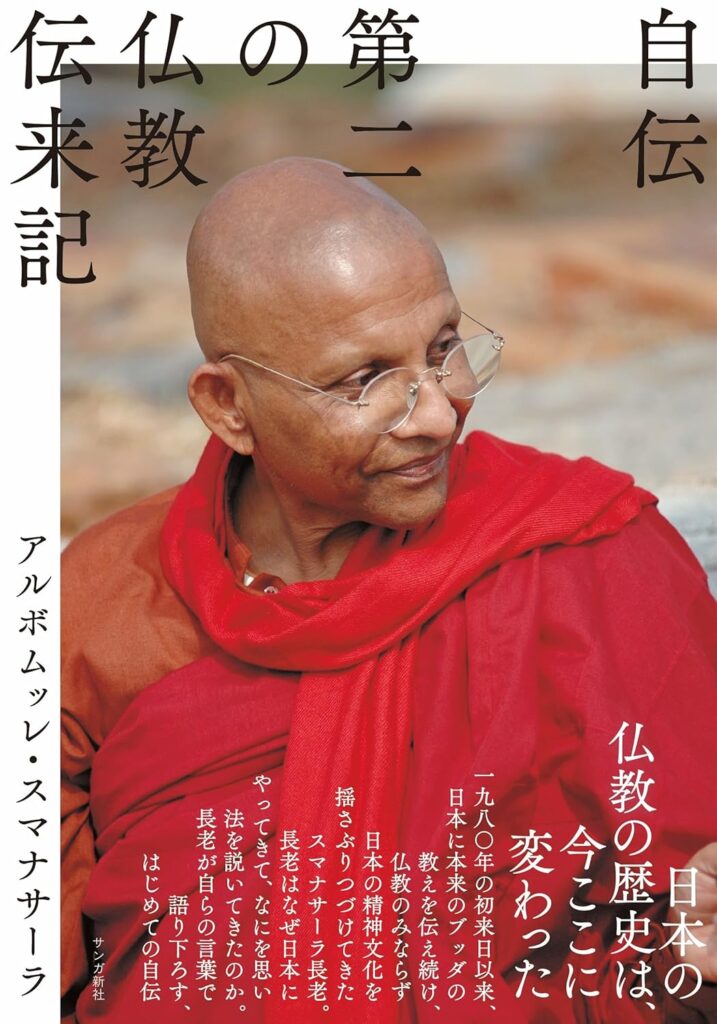
「自伝: 第二の仏教伝来記」
サンガ新社、単行本1,980円(税込)
アンガーマネジメントブームの発端となった著書『怒らないこと』をはじめ多くのベストセラーを生み、NHKをはじめ多くのメディアに出演、またマインドフルネスブームの先駆けとなるヴィパッサナー瞑想を普及させ現在の瞑想ブームを準備するなど、大きな影響を日本社会にもたらしたアルボムッレ・スマナサーラ長老。1500年の仏教の歴史を持つ日本で、初来日から今日いたるまでの45年の活動を通して、どのような思いでブッダの本来の教えを伝え続けてきたのか。幼少期からのエピソードも交えて、仏教の教えのエッセンスが凝縮したはじめての自伝。【アルボムッレ・スマナサーラ長老傘寿記念出版】
【目次】
はじめに─なぜ日本で教えを説くのか
わたしは今日だけを生きている/仏教を異文化に伝えること/
「仏教は宗教ではない」は革命的/日本語で説法をすること/穴に落ちたんです
■第一章 日本の活動
◎伝法初期 一九八〇年~一九八八年 初来日~駒澤大学大学院時代
ブッダの教えこそ伝えなくてはならない/留学の前/日本語の習得法/新聞で紹介される/赤い絨毯が敷いてあれば、去る/東京コミュニティカレッジでの講座/竹田倫子さんとの出会い/仏法学舎での問答/真面目に研究する人の態度/帰国
◎再来日 伝法を本格開始 一九九〇年以降
一九九〇年に再来日/ヴィパッサナー瞑想の指導を始める/さまざまな場で教えを伝える/大洋村/下町での暮らし
◎日本の人々とのふれ合い
子どもたちとの出会い/子どもの好奇心に学ぶ/管理される子どもたち/差別しない、気にしない生き方に接する
[コラム]
親殺しのある日本
日本の猿
◎日本で仏教を伝えるということ
人に問われれば真剣に喋るだけ/だれだってユニークな存在/語るベースは慈しみ/信ずるということ/文化の背景にある精神性の理解/わたしは挑戦を選んだのです/日本人にブッダの教えを伝えなくてはいけない/根本的な解決法を教える
◎日本で戒を保つ暮らし
比丘が守る戒律/テーラワーダ仏教の国の暮らし/お金は何のため?/人間は完璧ではないと覚悟する/起こるべきことが起きているだけ/修行を伝える
[コラム]
僧侶の団扇
■第二章 スリランカの思い出
◎スリランカのこと
スリランカのお寺/スリランカの独立/母の匂い/母の言葉/母から「死」を教わる/ある乞食の思い出/役を変えてみる/母の手料理/父親の思い出/父の世界/村の思い出/ゴキブリが好き/野菜を食べる猫/出家のきっかけ/出家したお寺
[コラム]
母からの自立
父のやさしさ
スリランカ社会における母親
[コラム]
学校の友だち
ほかの可能性
剃髪の薬草
出家のとき/負けるなよ/沙弥生活の始まり/瞬間で変わった心の体験/在家のおばあちゃんに教えられた「怒らないこと」
[コラム]
お寺のそばの動物園
動物たちとの会話
スリランカの迷信儀礼
◎師匠の思い出
面倒見のよい父親みたいな長老/人間として厳しく育ててくれた長老/師匠に差し上げた日本のお米/フクロウ先生/師匠の死/師匠のホロスコープ/瞑想道場の老僧/初めての説法
[コラム]
師匠を看病
■第三章 鬼籍に入られた方々の思い出
◎身近な人々の思い出
芦澤妙光さん/鈴木一生さん/小沼英子さん/江原通子さん/森田進さん/松井美文さん/岡田秀雄さん/島影透さん
◎日本仏教の人々
村上光照さんのこと/中村元先生のこと/奈良康明先生のこと/板橋興宗さんのこと/宮崎奕保禅師のこと
[コラム
教授の教え
■第四章 ブッダの教えを伝える
◎日本仏教とテーラワーダ仏教
日本の中の仏教/日本の良さと課題点
◎出版展開について
広く知られるようになっていく過程/本を出すということ/『怒らないこと』と『ブッダの実践心理学』シリーズ/ YouTube 配信/初期の出版活動
◎ブッダの教えを継承する
仏説について/お経はブッダの言葉の記録/パーリ語のお経について
◎ヴィパッサナー瞑想を伝える
実況中継/瞑想経典と注釈書/マハーシ式の教え方/その瞬間で起こることだけに集中すると二週間で悟れる
◎慈悲の瞑想を伝える
慈悲の瞑想について/この世は鬼の集まり/奇跡的に事態は変わる/慈しみを持つ人は無敵/生命は皆同じ仲間
◎教えの継承者
教えを継承するとは――自分が死んだ後のこと/弟子のポイント/師弟関係の難しさ
◎死を想う
ただ流れを観察する/死を迎えるとき/死に臨んで執着を捨てる
[コラム]
死の準備
死期を悟たおじいさん
マレーシアの大長老
前世を記憶する子どもたち/死の随観
[コラム]
人間以外に転生する
赤ちゃんの心
■アルボムッレ・スマナサーラ略史
編集者あとがき




